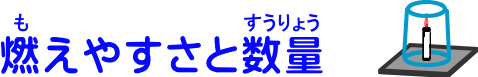コップの中のろうそくの火が消えるとき、閉(と)じこめられた空気の中に入っている酸素の濃度(のうど)は、どのように変わるのかな? 調べてみよう!
→ 外部リンク【NHK for School 燃えたあとの空気を気体検知管で調べると…】
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005301945_00000
(※ 日本放送協会ウェブサイトへリンク。アドレス確認日:2023年3月7日)
ろうそくの火が消えたとき、空気の中には、まだ酸素がたくさん残っていたね。
酸素があるのに、どうして火は消えたんだろう?
実は、ものが燃えるか燃えないかを決めているのは、周りにあるもの全部なんだ。
これから説明することは、とってもややこしいから、ゆっくり考えながら読んでね!
ものが燃えると、可燃物と酸素の粒(つぶ)が強く結びついて、たくさんの熱がでるよね。
燃えやすいものは着火源(げん)から十分な「距離(きょり)」をとることが「防火」のきほんだったね。
ものが燃えて出てきた熱を吸収(きゅうしゅう)するのは、可燃物と酸素だけじゃないんだ。火の中や火の周りにあるもの全部が、出てきた熱を分け合って吸収(きゅうしゅう)するんだよ。
例えば、コップをかぶせる前のろうそくの火の中や火の周りには、酸素と蒸発(じょうはつ)したロウのほかに、ちっ素がたくさんあるんだ。ちっ素は最初から空気にふくまれているよ。
→ 外部リンク【NHK for School 空気に含まれるさまざまな気体】
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005301115_00000
(※ 日本放送協会ウェブサイトへリンク。アドレス確認日:2023年3月7日)
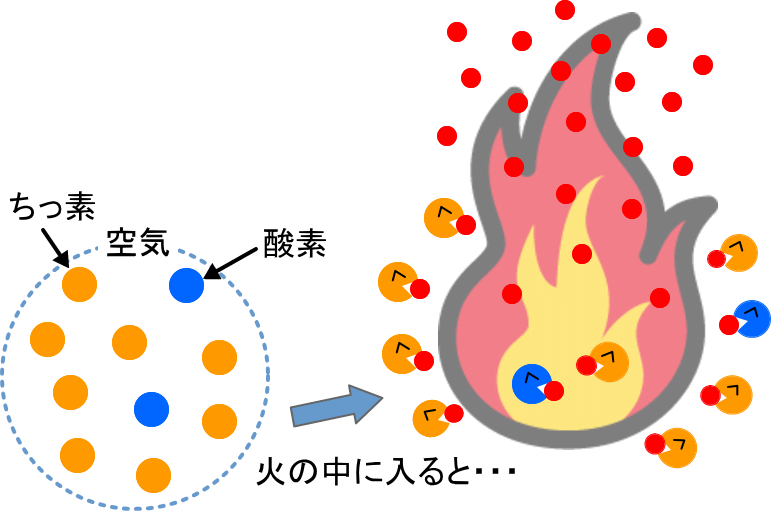
ろうそくが燃えるとき、蒸発(じょうはつ)したロウと酸素の粒(つぶ)が結びついて、熱が出るよね。出てきた熱は、まだ燃えていないロウと酸素と、空気にふくまれているちっ素が、分け合って吸収(きゅうしゅう)するんだよ。空気の中には酸素の約4倍のちっ素がふくまれているから、ちっ素に熱をたくさん取られてしまうけれど、それでも燃え続けるのに必要な高温を保(たも)ち続けることができる限り、火は消えないよ。
(※ 実際の火の中で発生した熱は、物質から離れて単独で存在しているのではなく、熱運動のエネルギーとして物質の内部に存在します。)
ロウと酸素の粒(つぶ)が結びつくと、二酸化炭素と水蒸気(すいじょうき)になるよ。火をつけたろうそくにコップをかぶせると、コップの中の酸素が減って、二酸化炭素と水蒸気(すいじょうき)が増えるんだ。ちっ素は、増えも減りもしないよ。
火の中に入る酸素が減ると、ロウと酸素の粒(つぶ)が結びつきにくくなるから、燃える速さがおそくなって、ろうそくの上の遠い所まで火が長く伸(の)びるよ。右下の写真の真ん中が、長く伸(の)びた火の様子だよ。
(※ コップをかぶせたときの火の変化の様子は、条件によってちがいます。)
酸素が減ると、火の温度も少し下がるよ。

こうして少なくなった熱を、コップの中にたまった二酸化炭素と水蒸気(すいじょうき)も、吸収(きゅうしゅう)するようになるんだ。二酸化炭素と水蒸気(すいじょうき)は、酸素やちっ素より熱を多く吸収(きゅうしゅう)する性質(せいしつ)があるから、濃度(のうど)は小さくても、二酸化炭素と水蒸気(すいじょうき)に熱を取られることによって、さらに火の温度が下がるんだ。
火の中の温度が下がると、ろうそくの芯(しん)に伝わる熱が減って、ロウが蒸発(じょうはつ)しにくくなるよ。 ロウが蒸発(じょうはつ)しにくくなると、火がだんだん小さくなって、出てくる熱も少なくなるよ。さらに火の温度が下がると、可燃物と酸素がエネルギーの山を越(こ)えて結びつく時間当たりの頻度(ひんど)が小さくなって、火が消えるんだよ。
ちっ素と二酸化炭素と水蒸気(すいじょうき)は、どれも普通(ふつう)の空気中では燃えない物質で、酸素のようにロウを燃やす性質もないよ。でも、火の中に入って、燃えているところで熱をたくさん吸収(きゅうしゅう)するから、ものが燃えるか燃えないかに大きく関わっているんだよ。もし地球の大気中にちっ素がふくまれていなかったら、私たちの身の回りにある多くのものが、簡単(かんたん)に燃えてしまうよ。
→ 外部リンク【NHK for School 酸素の中で燃やすと】
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005300239_00000
(※ 日本放送協会ウェブサイトへリンク。アドレス確認日:2023年3月7日)
火の周りでは、ちっ素などの気体だけじゃなく、すべてのものが熱を吸収(きゅうしゅう)するよ。固体や液体のロウも、ろうそくの芯(しん)もコップも、コップの周りにある物も、火の中から出てきた熱を少しずつ吸収(きゅうしゅう)しているんだよ。
物質の世界は、人間の社会と似ているね。私たちも、自分の活動とは関係のない周りの人から元気をもらったり、周りの人に元気をあげたりしているよね。社会を直接支えてくれているのは大人たちだけど、君たち子どもが、社会の一番の元気の素(もと)なんだよ!
防火のきほん(2): 数量(すうりょう)

防火の基本は、燃やすつもりじゃないものを燃えるくらいの高温にしないようにすることだったね。燃えやすいものは、着火源(げん)から離(はな)して、間に十分な「距離(きょり)」をとることが大事だったね。
ものを燃えるくらいの高温にしないように、私たちが注意できることは、距離(きょり)のほかに、何があると思う?
ものに熱が伝わったときに燃えるかどうかは、「可燃物」と「酸素」が「あるか・ないか」じゃなくて、「どのくらいあるか」によって決まるんだ。コップの中のろうそくの火も、酸素が全部なくなるよりずっと前に、熱が足りなくなって消えたよね。
熱は、可燃物と酸素が結びつくときに出るから、可燃物と酸素の結びつきやすさに関係のある、さまざまな「数量(すうりょう)」について知っておくことが、火事を防ぐために重要なんだ。
例えば、小麦粉のように体積にくらべて表面積が大きい可燃物を、空気中の酸素とふれやすい状態にすると、簡単(かんたん)に火がつくよ。
→ 映像資料を見てみよう!
 【粉じん爆発(ばくはつ)による火災の危険(きけん)】
【粉じん爆発(ばくはつ)による火災の危険(きけん)】
→ 外部リンク【NHK for School 灯油を燃やす】
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id=D0005300241_00000
(※ 日本放送協会ウェブサイトへリンク。アドレス確認日:2023年3月7日)